たそがれ
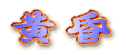
「あ〜あ、圭、帰ってこないなぁ」
僕は、これで何度目になるかわからないため息をこぼした。
もう圭が帰ってこなければいけないはずなのに、まだ帰ってこない。ずっと首を長くして待っているんだけど、そろそろ限界。圭不足が深刻になってきたみたいだ。
いつまで待っても圭が戻ってこないなら、こちらから行けばいいんだとようやく気がついたのは今日のこと。思いついたら急げとばかりに、オーケストラや大学、フジミの方にあれこれと連絡して、明日には出発する予定。
だから、今日はもうやることは何もなくて、こうして門の前でぼんやりと夕暮れの空を見つめているだけなんだ。
さっきまできれいな青空だったけど、日が傾くにつれてとても見事な夕映えが始まっていた。
「ねえ、なんか今日の夕焼けってすごくない?」
「なんか、ヤバイよな」
家の前を通り過ぎるカップルがそんなことを言いながら歩いていく。
確かにこんなに色鮮やかな夕日は珍しいかも。
凄みさえ感じさせる血のように色鮮やかな赤があたりを染め上げ、空と大地は赤と黒とに染め分けされていた。
まるで世界が変わってしまったかのような錯覚を覚えるほどで、帰路を急いでいるらしい人々の足もひそやかな歩みになっているようだった。
けれど、そんな風景もさほど長いことはなくて、まもなく色あせていくと普段と変わらない夕暮れの景色に戻ってしまった。
太陽は今まさに沈もうとしており、わずかな輝きが西の空に染まっている。そのときだった。
ぽつりと黒いしみが残照の中にあらわれ、少しずつ大きくなっていく。
それは次第に人間の姿となっていて、おぼつかない僕の視力でも背の高い男性だとわかるようになっていった。
「もしかして、あれは・・・・・?」
不安と期待と歓喜と諦観とが混じりあって、僕はその場に立ちすくんだまま人影が大きくなっていくのを息をのんで待ち続けた。
「・・・・・圭?」
必死で息を絞り、震える声で近づいてきた人影に呼びかける。
男性にはかすかな僕の声が聞こえたようで、ふっと顔を上げた。
「悠季?」
それは聞きなれたなつかしい声。
「こんなところに立って、どうしましたか?」
微笑みながらたずねてくる。まるで今朝出かけていただけのように軽い口調で。
「圭!よかった。帰ってきたんだね!!」
僕はうれしさで顔がくしゃくしゃになっているのを感じながら、圭のそばに駆け寄った。
本当は抱きついて思いきりハグしたかったんだけど、僕が走りよってくるのを見て圭がすっと足を引いた。
そうだっけ。ここは路上で、つまり公共の場所で誰が見ているかわからないから、今はそんなことをしたらまずいよね。
心からの歓迎と『お帰り』は、二人だけになってからのお楽しみということだ。
「お帰り、圭」
「ええ、ようやく君のもとへ帰れました」
疲れているのだろうか?微笑んでいる顔が少し青ざめているように見えた。
「さあ早く中に入って!」
僕は門を開き、圭を迎え入れる。
門を入るとき、きらりと圭の目が金色に光ったように見えた。でもそれは最後の夕日が反射したからじゃないかと思う。。
玄関扉を開き、中に入ったところで圭は浩一郎さんの額絵の前で立ち止まった。
「ただいま帰りました」
そうして、まるで彼と無言のまま何か会話をやりとりしているかのようにその場にじっと立ち尽くしたままでいる。
「圭?」
どうしたんだろうか。
「ああ、失礼しました。・・・・・ただいま帰りました、悠季」
「うん、お帰りなさい」
腰をかがめ、いつものように圭が僕に触れるくらいの軽い挨拶のキスをする。久しぶりなんだから本当は濃厚なキスが欲しかったけど、ここは玄関先だからしかたないよね。
圭は疲れているみたいだからセレモニーキスってことで、あとでゆっくり落ち着いてからだ。
「音楽室に行っていて。コーヒーを淹れるから。疲れてるだろうし、少し座っていて。あ、それともお茶か紅茶のほうがいいかな?」
矢継ぎ早に言い募ってしまった。圭が帰ってきて、うれしくてじっとしていられないんだ。そんな僕を見ていつものように微笑んで応じてくれた。
「それではコーヒーをいただきます」
「うん、ちょっと待ってて」
いそいそと台所へと行くと、僕はコーヒーを用意する。
いつ圭が帰ってきてもいいようにお気に入りの豆を用意してあったから、てきぱきとおそろいのカップにコーヒーを淹れ、お盆に載せたコーヒーを持ち音楽室に入ったんだけど、圭は少し眉をひそめてソファーに座っていた。なんだか怒っているみたいに見えるんだけど。
・・・・・何か問題でもあったのかな?
「コーヒーをどうぞ。僕は風呂を入れてくるよ。それとも腹減ってるかな?何か急いで作るけど」
また台所へと戻ろうとする僕の腕をつかまれた。
「悠季、少しお話があります」
「話って・・・・・?」
圭は僕を対面に座らせると、おもむろに口を開いた。
「ライティングデスクの中にこれが入っていました」
すっとテーブルにすべらせてきたのは数通の手紙。
「・・・・・あー、これ?」
思わず目をそらしてしまった。
これは僕が圭のところへ出かけるからって、福山先生やフジミのみんな、それに姉たちや宅島君に宛てた書置きだった。
「その、君のところへ行くんだから、そのことを知らせておかなきゃと思って」
「連絡なら電話で充分のはずです。なぜ手紙なのですか?」
「なぜって・・・・・」
僕は口を濁した。
「福山教授への手紙はまだしも、大学へのこれは退職届となっていますね。つまりこれは、書置きではない」
みるみるうちに、圭の視線が厳しくなっていく。
「悠季、これは遺書ですね?」
僕は思わず目を伏せた。
 |
 |
|---|
二つのルートがあります。
お好きな方へどうぞ!