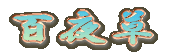
僕のもとに緊急の電話が来たのは、今から1ヶ月以上も前のこと。
圭が行方不明になった。
そういう知らせ。
圭は見たい資料が置いてあると聞いた図書館へと出かけていったという。そこがすぐ隣の街だからといってもヨーロッパでは距離も半端じゃない。
レンタカーを借りて一人で出かけたときの天候はよかったけど、急に崩れていって季節はずれの吹雪になってしまい、それきり・・・・・連絡が取れなくなった。
持っているはずの彼のスマホは、ホテルに置き忘れられていたのが発見された。
当然大騒ぎになって、向こうの警察や関係者たちがあちこち動いてくれて、圭が走っていったはずの道路沿いをくまなく探してくれていたけど、どうしても探し出すことはできなかった。
吹雪は翌日にはやんでだけどその後も天気はよくならず、ようやく天候が回復して改めて捜索されても足取りはまったく掴めなかった。
もうだめだ。きっと彼は・・・・・。
口に出すことはなくても、誰もが圭の生存が絶望的だと考えてるのがよくわかった。
でも僕はそんなことは信じなかった。
きっとどこかで救援を待っている。要領のいい彼のことだから、近くの農家かどこかにちゃっかり滞在していて吹雪がやむのを待っているに違いない。
そのうち平然とした顔できっと出てくる。
そう信じて、何度も現場に足を運んで探し回ったけど・・・・・。
やはり圭は見つからなかった。
圭の消息が掴めなくなって時は過ぎ、1週間、10日、20日、1ヶ月・・・・・。
そして、明日で7週間。49日。
昔、子供の頃にばあちゃんから聞いたことがある。亡くなった人がこの世に別れを告げるためにこの世に滞在できるのは49日なのだと。
それはつまり、残された家族たちが亡くなった者に対して、諦めと納得するための期間を意味しているのだろう。
でも、僕にとっては、圭ともう一度会うことができるかもしれない時間(チャンス)の期限を示しているように感じていたんだ。
だから、後のことをすべて整えて、明日には圭の後を追うつもりになっていたんだ。
どうやって向こうに行くかも――――ちゃんと考えてあった。
「おそらく君がそう考えるのではないかと思って心配していました。ですから、僕は必死で君のもとに帰ろうとしたのです。ですが、思っていた以上に時間がかかり、こんなに遅くなってしまいました。だがなんとか間に合ったようで、本当によかった」
圭がとても安堵した表情を見せるので、僕はとても申し訳なかった。
「心配させちゃったよね、ごめん。悪かったよ。でも僕は君がいないことに耐えられそうになかったんだ。だから、さ。ついていこうと決めてたんだ。でもさ、やっぱり君は僕のもとに戻ってきてくれた。だからこの手紙はもう必要ないんだよね」
そうだよ、圭はちゃんと戻ってきてくれたんだから。後追い自殺なんて考える必要はなくなった。
以前と同じように二人で暮らせるんだ!
僕はそう思って、ただただ嬉しがっていたんだけど。
でも――――。
「ねえ、圭。いったい今までどこにどうしていたんだい?それに、なんで日本に帰ってくるのにこんなに時間がかかったのか聞いていい?
なんでもっと早く連絡をくれなかったのかも知りたいよ。帰ってきてくれたのはとても嬉しいけど、せめて電話の一本でもしてくれていれば、こんなに不安にさいなまれることもなかったし悲嘆にくれるようなこともなかったんだ」
彼は生きていると信じていても、心のどこかにこのまま圭がいなくなってしまうんじゃないかという思いが消えなくて、ひどく不安にさいなまれた。まして後を追っていこうなんてせっぱつまった考えが思い浮かばずにすんだはずだ。
「いえ、そうではない。違うのです、悠季。僕は帰ることはできませんでした。少なくとも本来の意味では」
圭は厳しい表情を悲しげなものに変え、そっと僕の手をとって甲にキスして続きを言った。
「つまり・・・・・僕のからだは帰れなかった。帰ってきたのは思いだけ。僕はもうこの世のものではないのです」
圭は悲しげな表情を浮かべたまま、思いがけないことを言い出した。
「じ、冗談、だよね?」
僕は笑い飛ばそうとしたけれど、顔は引きつってしまった。
「・・・・・いえ、それは」
「だってさ!」
圭の言葉をさえぎり、ぎゅっと手を握り締めた。ちゃんと感触もあるし、ほらこんなにあたたかいじゃないか!
「幽霊だったら触れないはずだよ。君のジョークとしてはあまり出来がよくないね」
僕の言葉に圭はさびしそうに笑った。
「この家に入るまで僕は君に触れなかったでしょう?浩一郎氏のちからを借りることができたので、以前と変わりないように思えているのです。しかしそれは・・・・・錯覚のようなものなのです」
「嘘だ!」
僕は圭の首にしがみつく。そのままソファーに押し倒すと、噛みつくような勢いで圭のくちびるにむさぼりついた。
圭は僕のくちづけにいつものようにこたえてくれて、夢中になってむさぼっていたけど、どこかで圭の言葉が真実だと納得してしまう自分がいた。
からだを起こして圭を見つめると、いつものように穏やかに微笑んでいても、どこかもどかしくつかみどころのない存在に思えてくる。ふと、目をそらせば消えてしまいそうな存在感のなさは、僕もうすうす感じていたもので・・・・・。
ただ、認めたくなくて必死で目をそらしていただけなんだ。
「君にもわかったでしょう?」
「だったら!君は僕を迎えに来てくれたんだよね。昔約束したもの。君が逝くときには僕も連れて行ってくれるって!」
そうだよ。圭が一緒に連れて行ってくれるなら、どこだっていく。たとえそれがあの世だって、地獄だって、どこでもいいんだ。
「ねえ、悠季。僕の話を聞いてもらえませんか?」
穏やかな声が僕の激情を優しくなだめてくる。
「僕には計画していたことがたくさんあるのですよ。君と一緒にしたいことも、君にしてあげたいことも、それは君がうんざりするくらいたくさんね。ですが、それが今はできなくなってとても残念でたまらないのです」
圭の頭の中ではきっとオーケストラのことやフジミについても、きっとたくさん計画ができていたに違いないけど。
「ですから、僕と一緒にいくのは待っていただけませんか?僕がやりのこしたことを継いでやりとげて欲しいのです」
「それ・・・・・は」
イヤだ!
と言いたかった。でも、圭がからだを起こして僕の両手をとって語りかけてくる言葉には、悔しさがにじんでいたから。
「・・・・・そうだよね、君はたくさんやりたいことがあったんだよね」
圭の隣にいた僕には、ロマンティストで実行力のある圭の思いが少しはわかっていたつもりだから、彼が道半ばで退場しなければならないことがどんなに無念か、理解できる。
「ええ、そして僕の遺志を継いでくれるのは君しかいないと思っています」
静かな声には、切なさと必死さが含まれていた。
確かに圭が行方不明になってしまって、オーケストラは空中分解の危機を迎えている。オーナーであった圭がいなくなったら、求心力はなくなってしまうし、スポンサーだっていなくなってしまうかもしれない。
それを守ることができるのは、残された僕しかいない。そのことを、昨夜宅島君にも言われていたけど、必死で耳をふさいで聞こうとしなかったんだ。――――後を追うつもりだったから。
僕はここに残らなくちゃいけないのか。彼の望みをかなえようとするならば、今は圭のもとには行けないことになる。
「・・・・・だったら圭、幽霊だってかまわないじゃないか。こうやってここに来てくれているんだから、浩一郎さんと一緒にここに住んで、僕と一緒にいてよ。これが夢のようなものだって言うなら、毎晩会いに来てくれればいいじゃないか。そして僕に指図してくれれば君の言うとおりにしてみせるよ!」
我ながらこれはいいアイディアじゃないか。圭が僕のそばにいてくれるのなら、なんだっていいんだから!
「いえ、それはできません」
きっぱりと否定された。
「できないのですよ悠季。今夜まではまだ夢の続きでいられました。ですが、明日の朝になれば真実がすべてを崩壊させることになり、もう夢にはできなくなるのです」
浮かれていた頭がさっと冷えた。
「・・・・・それって?」
圭は顔を伏せた。
「宅島から連絡が入るでしょう。・・・・・僕が発見されたという」
ああ、だから圭は今夜のうちに僕に会わなければならなかったのか。僕にどうしても伝えなければならないことがあったから、こんな思いがけないやり方で会いにきてくれたんだ。今夜が唯一のチャンスだったんだ。
それなのに、僕は彼の願いを無視するのか?彼が必死で頑張っていたやりかけのあれこれを、どうでもいいように扱って無視して、投げ捨てるつもりなのか?
けれど、その先の言葉を口にするのは、とてもつらかった。でも・・・・・言わなくちゃいけないんだよね。
「・・・・・少しだけなら。僕にできるほんの少しなら、君が望んでいたことを次の人に伝えるためにがんばってみる。それから、君のところへいく。そのときは土産話をたくさん持っていくから」
「ありがとう、悠季。ええ、君の話を楽しみにしていますよ」
嬉しそうに微笑んでくれた。
そしてわかったんだ。彼がここに来たもうひとつの理由。
圭は僕に後を追って欲しくないんだって。
僕だってわかっていたんだ。自殺者が行くのは圭とは違うところかもしれないって。でも僕は、圭がいない現実がつらくて、逃げ出そうとしていたんだ。
そんな僕を心配して圭はやってきてくれた。こんな無茶をしてまで。
でも・・・・・だから。
「明日の朝までならこの夢は続くんだろう?だったら圭、僕を抱いて!君が僕のところに来てくれたんだって実感させて!!」
「・・・・・明日の朝になれば、すべては幻になってしまいますよ。むしろつらくなるかもしれない」
「僕が覚えている!僕の記憶の中だけにあればいいんだ。だから、圭!」
僕の必死さに、圭はほんのりと微笑んでくれた。
「君の望むままに」
そう言うと圭と僕は手をつなぎ、二階へと向かったのだった。
その晩の圭はとてもやさしくて丁寧だった。
圭とのセックスの中で、発見されたり覚えさせられたりして感じてしまうようになったところをくまなく愛撫してくれていて、僕はもう何も考えられなくなるほど圭とのセックスに溺れ、貪欲に求め続けた。
「圭、圭・・・・・けい・・・・・!」
沸騰してしまったかのようにからだが熱い。あえぎでのどはひりつき、涙で目はかすむ。
彼の望むままにからだを開き、すべてをさらす。
いつのことだったか。圭が四十八手を試してみませんか?とそそのかしてきたことがあって、うっかり僕はそれに乗せられたことがある。
男の股関節じゃ無理なポーズがいくつもあったのに、そのときの勢いで望むままにからだを屈曲させて圭を受け入れ、翌朝にはたっぷり後悔したものだ。
でも今夜はそんな後悔はしない。たとえ朝になって動けなくなっても、たとえあちこちが壊れてしまったとしても、それは本望というものだった。
「あっ、ああっ、ああ・・・・・ん!けい、けい・・・・・け・・・・・い・・・・・!」
のどからほとばしる悲鳴のような声。
けれどそれは自分でも恥ずかしくなるくらい甘く蕩けていた。
「も、もう・・・・・圭、いっちゃう・・・・・!」
「ええ、悠季。僕もです。いきますっ!」
もう何度目かの絶頂の波にさらわれて溺れ、そして僕は圭をむさぼり尽くす。
もう腕も上がらず、目を開けていることさえつらいくらいで、圭の胸に耳を押し当てて彼の鼓動が次第に穏やかなものに戻っていくのを聞いていた。こんな時間がとても好きだ。
でも・・・・・。
「圭、ねえもっと」
たがが外れてしまっていた僕は、かすれた声でそんなふうにより多くを望む。
しかし圭は、意を決したかのようにそっと僕から身を離してきた。
「・・・・・圭?」
「もういかなくてはなりません」
気がつけば時間は過ぎていて、なんとか枕もとの時計を見るとまもなく夜も明ける時間。
狂乱のときは終わったのだ。
「圭、いかないで!」
未練な僕は必死で訴えた。
けれどベッドから起き上がった彼は、僕がなんとか起き上がろうとのろのろともがいているうちに、あっという間に身支度を整え終えていたのだった。
僕はというと、いまだに足腰が立たず、ベッドから起きることも無理そう。
「愛しています、悠季。さあ、このままお眠りなさい」
そう言ってやさしいキスをする。でもこれは・・・・・別れのキス?
ゆるやかにまぶたが下りてくる。なんとか必死で目を覚ましていようとしているのに、どんどんからだは重くなり、睡魔は容赦なく襲ってくる。
「・・・・・ねえ、圭。僕がそっちへいくときには迎えに来て。君を失望させないようにがんばって・・・・・いく・・・・・から」
語尾のゆるんだ声でなんとか僕の意思を伝えようとがんばった。圭に心配させないように。
「ありがとう、悠季。ええ、必ず迎えにうかがいます」
昨日までの暗い淵のような絶望感や焼けつくような痛みは僕の胸にない。昨夜の狂乱が焼き尽くしてくれたのかもしれない。
胸に残っているのは、切なく透明なあきらめ。そして、かすかな希望。
「愛してますよ」
「ん。僕も・・・・・」
圭は僕の手首をとるとキスをした。ちりっとした痛みが走ったからキスマークが残ったかもしれない。
「・・・・・でも、夢なら・・・・・きえちゃう・・・・・んだよ・・・・・ね」
「おやすみなさい、悠季。また会いましょう」
そして、暗転。
次に目が覚めたとき、なかば覚悟していたけど、圭がいた形跡なんてまったく残っていなかった。
気がつけば、僕は服を着たままベッドに横たわっていた。あたりを見回しても昨日と変わった様子なんて何もない。
あれほどハードなセックスをしたはずなのに、ベッドには何も残っていないし、僕のからだはどこにも筋肉痛なんてなくて、ガタがきているなんてこともない。
でも、僕は圭にコーヒーを出したはずだ。あれはどうなってる?
急いで階段を下りていったみたけど、ピアノ室の中に誰かが来たという形跡は残っていなかった。
部屋の中にただようのはコーヒーの香りではなく、窓辺の花瓶に生けてある菊の花の清冽な香り。コーヒーカップはいつもの場所に置かれ、淹れたはずのコーヒーも減っていない。ゴミ箱の中も同様に。
すべて消え去っていた。
思わずこぼれた深いためいき。
彼が言ったように、すべては夢に帰結した。ここに圭がきていたという証拠は残されていなかったのだ。
ふいに電話がけたたましく鳴り出して、びくっと身がすくんだ。
音はいつもとかわらないはずなのに、どこか不穏な音色をしているように思えた。
その電話が何を意味しているのか、十分わかっていたからだ。
そして僕が受話器を取るのをためらっているうちに、自動的に留守電へと変わっていた。
《あー、宅島です。朝早くから申し訳ない。重要な話があるので、これからそちらに説明にうかがいます。守村さんは出かけずに待っていてください。・・・・・それから小夜子さんも同行するそうです。では、のちほど》
重要な話というのは、おそらく圭がみつかったということだろう。
僕が話を聞いたら衝動的に何かやらかすんじゃないかって心配して、直に説明しに来てくれるんじゃないのかな。昨日までの僕ならありえることだった。
でも、圭と約束したんだから、そんなことはもう考えない。
僕は昨夜のあれこれを思い出して、またため息をこぼした。
圭のケチ。せめて少しくらいここに来てくれたっていう証拠を残してくれたっていいじゃないか。せめてキスマークくらい。
そう思いながら、僕は眠りに落ちる前につけていったはずの手首を見る。
「な、なに?」
そこにはうっすらとうすいアザが残されていた。
誰に話したところで夢でキスマークをつけられたなんて信じないだろう。そんな薄紅のアザ。
でも、僕は信じる。これは圭が僕に残したメッセージ。
ぽたりとしずくが手首に落ちた。
「あれ?」
ぼやぼやと視界がにじむ。そして涙があふれているのに気がついた。圭がいなくなってから、ずっと流れることがなかった、いや、流すことができなかった涙が。
「守るよ。きっと君との約束は守る。だから圭、見守っていて。きっと僕は君の遺したものを守っていくから」
僕は白い朝の光の中、たったひとりで誓いを立てる。
残されたキスマークに、そっとくちづけながら。
 |
|---|
| お分かりになった方もいらっしゃると思いますが元ネタは雨月物語の中から、「菊花の契り」 タイトルの「百夜草」は菊の古名だそうです。 菊にするとばれると思いましたので、変えさせていただきました。 |
|---|
2014.12/27 up
