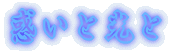 |
|---|
「お帰りなさい、親方」
「あれ?迎えに来てくれたんだ」
悠季が九州の演奏旅行から戻って、羽田空港に到着してみると、ロビーでは宅島が待っていた。
「僕はこのままタクシーで帰るから迎えに来てくれなくてもよかったのに。圭にもそのように言ってあったし、君は圭の仕事についていくことになっていたんだろう?」
「ええ、まあ。そうなんですけどね」
彼は歯切れ悪く言うと、悠季の荷物を受け取って駐車場へと案内してくれた。
止めてあった車に乗り込んで走り出したけど、いつものような気軽な雰囲気がない。
何かあったのだろうか
車が首都高に乗って落ち着いたところで、彼に聞いてみた。
「そろそろ話してよ。圭に何かあったの?」
「はあ。何かあったわけではないんですけどね」
やはり煮え切らない。
「じつはですね。ボスが一昨日あたりからひどく機嫌が悪いんですよ。
ぴりぴりとしているのを無理に隠しているし、俺が見ていないときには睨んでくるし。何か気が触る事でもしたのかと思って、思い切って尋ねてみても、何もないと言い張るしですね。
困り果ててしまったところなんですよ」
「うーん。おかしいねぇ。一昨日までは別に変わった様子はなかったと思うよ。昨日はホテルに帰るのが遅くなったんで、メールを送って電話はしなかったんだけど」
プライベートのときや悠季の前ならふくれたりすねたりもするが、仕事の場では自分の感情をあからさまにすることを嫌う彼がいったいどうしたというのだろう。
「それで、僕に何があったのか尋ねてほしくて羽田まで迎えに来てくれたってわけかい?」
「いや、そうじゃないんです。迎えに寄こしたのはボスなんですよ。
親方が迎えは必要ないから迎えに来なくてもいいと言っていたのを承知の上で、俺にどうしても迎えに行くようにと厳命してきたんです。
もしできるなら自分で迎えに来てたでしょう。リハーサル中に抜けるなんて出来ませんからね」
「そう、なんだ」
これが長期の演奏旅行の帰りなら、圭に迎えにきてもらえれば嬉しいしありがたい。
でも今回のコンサートは二日間だけの短期だし、圭は仕事中。わざわざ迎えに来てもらうほどのものではないからと断っていたのに。
「とにかく、そんな具合なんです」
「うん、わかった。それとなく圭に尋ねてみるよ」
「すみません。実はトラブルが俺に対してだけじゃないのでよけいに困っているんです。M響の飯田さんと五十嵐さんにも俺と同様の困った態度をとっているようなので」
いったいどういうことなのだろう?
安定した精神の持ち主である圭が、むやみに他人に対して攻撃的になる事はない。まして二人はフジミのメンバーなのだ。
フジミのことを大切に思っている彼がどうしてそんなことをするのだろうか?
悠季が富士見町の我が家へと送られてきて、宅島の車が戻って来るのを見送ってから中に入ると、どこかに違和感がある。
何が違っているのかとしばし首をひねって考えていて、ようやく写真の数が増えている事に気がついた。
出かけて言った時よりも、明らかに幾つも写真立てや壁の写真フレームが増えているのだ。それも二人で撮ったものではなく、自分一人が写っているものも幾つか。
「うわっ!これは禁帯出のヤツじゃないか」
今までは圭秘蔵のアルバムの奥に仕舞いこまれていた写真のはず。
ベッドの中で全裸だと分かる格好のままこっちを向いて笑っている。よく見れば肩のあたりにキスマークがあるのまで・・・・・わかる。
一人の写真だから、これだけなら寝起きのところを写したと言い張る事も出来るかもしれないけど、ワケありの人たちに見られても平気な顔を出来るかどうか。
「なんでこんな写真をここに置くんだ?」
圭の変調ぶりは他にもあった。
冷蔵庫の中をのぞいてみるとたくさんの食材が買いこんであったけど、どれも調理途中でまた冷蔵庫に戻されているように見える。
結構手の込んだ料理を作るつもりで、時間が無くなったとか?でもこんな中途半端をするなんて、几帳面な圭らしくない。
着替えをしようと二階へあがると更におかしい。
絶対に誰にも見せられない秘蔵の写真――――ベッドの上で二人が裸で座っている――――がいくつもベッドの上に散乱している上に、悠季の服までが引き出しから出されていた。
いったいどうしたんだろう?
悠季は困惑と不安を抱えながら、秘蔵のアルバムの中に全ての写真を元通り入れ直し、服はきちんとクローゼットにしまい込んだ。
シャワーを浴びて着替えて、下へと降りてきて、さて、では完成しなかった圭の料理を仕上げる事にしようかと考えて、あれこれと献立を考えた。
時間がなくて手に負えないと思えるものはそのままにして、出来そうな料理を仕上げると、圭が帰宅するのを待つことにした。
ジリリリン
ドアベルが鳴って、悠季は玄関へと急いだ。
「お帰り」
ドアを開けると、圭が立っていた。
「・・・・・ただいま帰りました」
いつもならすぐに返事をするのに、今日は悠季の顔をじっと見つめてから、ゆっくりとかみしめるかのような口調で言った。
こわばっていた顔がゆるみ、ほっとしたように微笑んで悠季を抱き寄せていつもの圭に戻ってキスしてきた。
普段よりも更に情熱的なキスのせいで、悠季のからだの芯にぽっと熱が生まれたけれど、そのまま流されてはせっかく作り上げた料理が無駄になりそうだった。
「風呂が沸いてるから入るかい?夕食は盛り付けるだけになってるから、先に食べてもいいし」
「・・・・・ええ、そうですね」
何か考えているのか上の空の返事が返ってきた。
圭の手はまるで悠季を存在を確かめるかのように、髪を撫で、頬を親指の腹で触れ、首筋から肩へ背中やウェストをさまよう。
「圭?」
「ああ、すみません。風呂を先にします」
どこか失調した口調で、二階に着替えに行ってしまった。
悠季は、これは深刻なことになりそうだと、小さなため息を一つこぼしたが、下へ降りてきた圭には心配そうな素振りを見せるわけにはいかなかった。
「悠季、一緒に入りませんか?」
「うーん、どうしようかな?」
圭と一緒に入ることは問題ない。いや、嬉しいことだけれど、数日の不在の後となれば、絶倫の圭が何もせずに離してくれるとは思えない。
風呂の中で事に及んでしまえば、食事をすることなど頭から飛んでしまったこともあり、体力のない悠季ではそのまま起きられずに朝を迎えてしまったことも、幾度か。
食事のことだけでなく、何があったのかとうまく圭を問いただすにはそれなりの気力が必要だけど、圭に付き合っていては朝まで啼かされることになるかもしれない。
そうなったらもう何か言うだけの体力さえ残っていないに違いない。
何も出来なくなってしまうことになる。
でも、何も聞かずに彼の好きなようにさせてもいいかもしれない。それで圭の気持がほぐれてくれるなら。
そう思い直して、にっこりと笑ってうなずいた。
「いいよ。先に入っていて」
「そのままなしくずしにベッドインなどという無粋なことにはしませんよ。君がつくって下さった夕食を無駄にするわけにはいきません」
「あはは。うん、久しぶりに一緒に食事をしたいよね」
先に圭が風呂に入っている間に悠季も着替えを用意して中へ入った。
ざっとかけ湯をしてから、ぬるめに焚いた湯につかっている彼の隣りへと入る。
うながされて背後からだっこされる形になった。
普段ならまるでアペリチーフを愉しむように触れたりおしゃべりで楽しんだりするのに、まるでしがみついているかのようにぎゅっと抱きしめてくる。
「圭?苦しいよ」
「ああ、すみません」
手をはなすといつものように軽く腕を回してくると、ふっとため息が首筋にかかるのを感じた。
「実は今度フジミでバーバーの曲をやってみようかと言う話が出ていまして・・・・・」
普段の彼の声の調子に戻って、悠季が留守の間のフジミの様子などを話し出してきた。
「へえ。面白そうだね」
話を合わせつつも、迷っていた。
何を聞きたいのか、薄々は察しているんじゃないかと思う。それなのに話し出さないのは、やはり彼が話したくないということかもしれない。
「のぼせそうですね。先に上がります」
圭が出て行ったので、悠季も急いでからだを洗って風呂場を出た。
料理を並べようと台所へ入って行くと圭が既に料理を並べて待っていてくれた。
「悪い。僕がやるつもりだったのに」
「いえ。並べるだけならたいしたことではありませんよ」
微笑みながら悠季の方を向いた。
圭のぱらりと前髪が落ちていて、いかにもくつろいだという雰囲気が出ている。
濡れているせいで、髪がいつもよりも黒々とした艶があり、肌の奥に湯上りの温もりがあるせいで、いつもよりも男っぽい色気があるようでどきりとした。
「僕が作りかけていた食材で作ったものですか?」
「ああ、うん。せっかくいい食材があったんだから、ちゃんと作って食べなきゃもったいないからね」
「ありがとうございます。美味しそうですね」
「君ほど凝った料理には出来なかったけどね。気にいってもらえればいいな」
一緒に箸をとって、互いのあれこれのできごとを話しながら食事を進めていったが、悠季にはあまり味が感じられなかった。
食事を済ませ、後片付けを済ませると圭がぎゅっと抱きしめてきた。
「悠季、食が進まなかったようですね。宅島に言われた事が気になっているのではありませんか?」
「ああ、うん」
どうやら自分から言い出すことにしてくれたらしい。
「君はいったい何を悩んでいたんだい?もし話せることなら話してくれないか?宅島くんも心配していたよ」
「ええ。迷惑をかけてしまいました。彼からの電話で君に頼んでいた事も聞きました。そのことについては、まずこれを見てください」
手渡されたのは薄い写真週刊誌だった。
「これって、以前君とSポンとのゴシップ写真をでっち上げた雑誌?」
「いえ、あれとはまた別の雑誌です。実は今日発売のこれに僕が出ていまして」
話を聞いて、悠季は急いで雑誌をめくってみた。
すると、なにやら女性の腕をとって親密そうにしている圭の写真が出てきたのだった!
「先ほど宅島から手渡されました」
そう言って、先ほど聞かされた話を教えてくれた。
「ボス」
帰宅する車中、信号待ちの間に宅島が話しかけてきた。
「何かありましたか?」
「あー、ボスの機嫌が悪い理由が分かりましたよ。申し訳ない、これは俺のミスだ」
富士見町へ車を運転しながら話しかけてきた宅島の言葉に、圭は黙って話の先をうながした。
「今日発売のSaturdayという雑誌のゴシップ写真のことを心配していたんでしょう。それとも、もう読みましたか?」
「いや、買っていない」
「それじゃこちらをどうぞ」
宅島が手渡してきた雑誌には、アイドル女優とのツーショット写真が大きく掲載されていた。
先日、圭はある企業が開催したミニ音楽祭に出演することになった。
圭が指揮をし、小編成のM響団員が演奏を担当したのだが、その司会のアシスタントとしてくだんのアイドルが起用されていた。
ミニ演奏会は盛況の内に閉幕し、その後、スタッフやM響のメンバーと共に圭も打ち上げに参加していた。
「打ち上げ会場から出てきたときに撮られたのだと思うが、この時は周囲に何人もいたはずです」
「確かにそのとおり。たまたま二人だけが離れた時をねらって撮られたんだろうと思いますよ。これくらいの写真が大きく掲載されるというのは、彼女の事務所が話題づくりを狙って押し込んだものかもしれない」
「ありそうな話ですね」
「出版社に抗議するか?」
「いえ、放っておきましょう。こちらが騒げば更にマスコミを喜ばせる事になる。思うつぼです」
「確かに。それじゃこの件について、何か言われる前にM響に状況報告をしておきます」
「ええ、よろしく」
「なるほどね」
悠季は、車中で交わされたという話を聞いた後、手渡された問題の記事の写真をじっくりと眺めた。
普段、女性に対しては無愛想な彼にしては珍しく微笑んでみせている。
それだけでちょっとむっとなるような場面だったが、よく見れば笑顔は彼女に向けたものではないようにも見える。
トリミングの妙によって、立派なデート写真に作られていた。
「もしかして、この端に写っているのって飯田さんじゃないか?それにこの頭は五十嵐君にも見えるし」
知らないものが見れば通行人が写り込んだように見えるだろうが、隅に半分だけ写っているのは確かにM響の二人だった。
「ええ。僕の記憶によれば、この時五十嵐君の冗談に笑っていたと思います」
「そうかあ。もしかして、飯田さんたちへの態度が悪かった理由って、この記事のせいだったのかい?つまり君はこの記事が掲載されるかもしれないって知っていたわけ?」
「・・・・・はい、・・・・・いえ」
圭はためらった後、渋々答えた。
「フラッシュがたかれて写真を撮られたようだとは思っていましたが、それがパパラッチによるものなのか、通りすがりのファンが撮ったものなのかは判別できませんでした。撮られても別段困るような状況ではありませんでしたから無視していました」
「それなのにこんな写真に仕立て上げられちゃうなんて、怒るよね」
「これくらいのことでしたら大したことはありません。・・・・・ですが、今回僕の様子がおかしかったのは、この記事が原因だと思って宅島は納得したようですが」
「別の理由があるってわけか。そのわけを聞いてもいいかな?」
「言えばおそらく君は呆れることでしょう。いえ、軽蔑すると思います」
「君が言いたくないのなら、無理に聞くようなことはしないよ」
そう言って、手を伸ばして圭の手を握った。
ぎゅっと握り返してくれる、手のぬくもりがあたたかい。
「いえ、君には僕の本当の気持ちを知ってもらいたいと思います」
優しい微笑みを浮かべて圭が言う。
「実は・・・・・夢を見たのです」
言ったとたんに不安そうなまなざしで悠季を窺ってきた。
「夢?」
言われた悠季は、意外な言葉に困惑していた。
「君がここに存在しないという夢でした。
まるで、現実のように細部まではっきりとしていて、実際に起きている事なのだと信じてしまうほどにリアルだったのです。
そこでは『守村悠季』という人間はどこにもいなくて、誰も知らない。
宅島も飯田君や五十嵐君、更には石田君もが口をそろえて君の存在を否定したのです。
君がいないというのに、僕以外の者に違和感はなくて、つじつまは合い、破綻は起きていない。
・・・・・恐ろしい状況でした。
最後の望みを賭けて新潟へと出向いたのですが、あの場所に守村家は立っていても、やはり君は存在していないのです。
僕にとってどんなものより見たくない悪夢でした。
悪夢だと言い聞かせても、君の姿がそばにない。
それで、不安が拭いきれなくて・・・・・だんだん強迫観念にかられてしまったようで、飯田君たちに八つ当たりするような羽目になってしまいました」
身を震わせ、ぎゅっと両の手を握りしめていた。子供のように悠季に抱きつきたいのをぐっとこらえているのかのように。
「それで、周囲に向かって不機嫌オーラを撒き散らしていたわけなのか」
「不徳の致すところです。抑え込んでいたつもりだったのですが」
「君がちょっと睨んだだけでも、周りはビビってしまうからなぁ」
悠季はくすくすと笑った。
「あきれたでしょう?大のおとながこんなことで動揺しているのですから」
「うーん。僕は君の『ベベ』な姿をいくつも見ているから・・・・・なんてね。君にとっては何より恐れていた事だってことは分かったよ。
あきれたりはしないよ。僕にも心当たりがあることだから」
ふと真顔になって圭へと向き直った。
「以前僕が言った事があるだろう?『僕なんて君にふさわしくない。いつか君に捨てられる時が来る』そんな怯えが心の奥底にあるんだって。そんな不安と同じようなものじゃないのかなって、そう感じたんだ」
「そう、なんでしょうか」
ためらいがちにいう圭に、悠季はうなずいてみせた。
「だとしたら、僕と同じアドバイスが効くと思うよ。年月がいつかそんな不安を融かし消し去っていくだろうってね」
悠季の笑顔はおだやかで、圭の不安をたいしたことはないとなだめてくれる。
「・・・・・はい」
それでも、圭の顔からは不安が拭い去れない様子が残る。
悠季は圭の手を取ると、自分の顔にあてさせた。
「僕はここに居る。誰かが何と言おうと、君だけは僕がいることを信じ続けて。そうすれば大丈夫。君は僕を見つけてくれた。だからここに居るんだ」
緊張していた圭の口元がふと緩んだ。
「・・・・・はい。ええ、確かに僕は君を見出しました。どこにいるか、誰なのかも分からない君を。ならば僕が信じる限り君は居てくれるのですね」
ぎゅっと抱きしめて、ぬくもりを確かめた。不安にさいなまれてすがるわけではなく、愛する者を信じるために。
「ああ、目を閉じていても君の匂いが君がここにいることを教えてくれる。僕の手が君のぬくもりと重みを感じさせてくれる・・・・・。確かに君がここにいる・・・・・!」
柔らかなキスと愛撫で悠季の形をなぞるように確かめる。
ゆるやかで執拗な触れかたは、悠季の中に熱とじれったさを溜めこんでいく。
「ベッドへ行きましょう」
「・・・・・うん」
「今日は、朝まで君を離せないと思います」
「・・・・・覚悟するよ」
「手加減出来ないかもしれません」
「・・・・・なるべく手柔らかにね」
「努力します」
| 話の続きより先にHシーンが見たい! なら 「夜の真実、朝の現実」へ行きます |
|---|