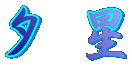
悪魔が来たりてパソを打つ・・・バージョン(笑)
僕は『そんなことはない、君の気のせいだ』と笑って答えようとしたのだが、唇からは声が出ず、笑おうとした顔はぶざまに歪んでしまった。
ゆうきは僕を黙って見ていたが、そのうちふいに僕のからだを抱きしめてきた。温かくて小さい手のひらは僕の背中をぎゅっと抱きしめてから、ぽんぽんとやさしく叩き、背中をなでさすってくれる。そんな風に無防備に抱きしめられた記憶のなかった僕は、驚いて固まってしまった。
ゆうきの子供らしく熱いからだは、お日様と花のようないい匂いがしていた。ぽんぽんぽん・・・・・と鼓動よりややゆっくり目のそのリズムは僕の中に凝っていた冷たくて固いものを少しずつ少しずつ緩やかに溶かしていくような気がして・・・・・気がつくと僕はゆうきのからだに手を回し、彼のからだを抱きしめ返していた。
細くて華奢なゆうきのからだは、抱きついてみると、とても感触がよかった。そうしてゆうきのやさしい匂いと気持ちのよい抱擁は、何かを僕の中にそそぎ込み満たしていくように感じられた。
ふいにゆうきの小さな唇が僕の唇に押し付けられた。僕の唇を熱くて小さな舌が割って侵入してくる。僕の口の中を探るようにして入ってきた舌は、びろうどのような感触で僕の舌をなでていき、そうしてそっと丸くて硬いものを舌の上に乗せてから、僕の唇を離れていった。
ゆうきが僕に口移しで渡してくれたのは、小さな飴だった。優しい彼が差し出してくれた小さななぐさめ。
「美味しいよ。圭にあげる」
「・・・・・ありがとうございます」
僕は素直に渡された飴をなめて味わった。飴は濃厚な乳の味わいで、素朴でやさしい甘さを持っていた。
「・・・・・とても美味しいです」
「そう、よかった!」
確かに飴は美味しかったが、もっと美味しかったのはゆうきが僕に与えてくれたくちづけで、柔らかな唇と僕の口の中をひらめいていった熱くてびろうどのような舌がとても官能的で、僕をドキドキさせていた。
ゆうきは、僕を抱いていた手をほどいて姿勢を戻し、にっこりと笑って見せた。ゆうきにはただ単純に友達に飴を分け与えたいと思っただけだったのかもしれなかったが、僕にとっては興奮するキス・・・・・性愛に対して初めて興味を持った出来事だった。
もっとキスして欲しい、もっと僕を触って欲しい・・・・・。そんな気持ちが湧き上がってくる。
僕はさらに呆然となり、先ほどまで僕の心を苦しめていた事柄が、どこかに飛んでしまっているのを感じていた。
きっと今の事に気がついたらからかってくると思っていたまさゆき君は、男同士として僕の姿を見ないように他所を向いていて、知らぬ振りをしていてくれたらしい・・・・・。
――そう。あれは僕の初恋だったのだ。――
あれから十数年たち、僕が大人になった今でもあの出来事は僕の中で暖かく大切な思い出となって生きている。
そうして僕が那由他に【暁皇】の船長として出かける度ごとに、あの飴を手に入れる。
口にあの甘い飴を入れる度にやさしいゆうきの顔が思い浮かび、あの幼くても印象的だったくちづけの記憶が僕を悩ます。今の君は、少しでもまだ僕のことを覚えていてくれるだろうか・・・・・?
僕はいつか必ず君を探し出してみせます。ええ、きっと・・・・・!
薄暗くした寝室のベッドの上で、僕はまた彼の記憶を呼び覚ます。
そうして、僕の右手は、ゆっくりと下へと降りていった・・・・・。
あ、あははははは・・・・・。(;^_^A
何も言う事はございません。
2006,6,27 Re up