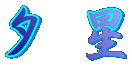
僕は宇宙船の中で生まれ、宇宙船の中で育ち、ある程度大きくなるまで惑星に降り立つ事が許されなかった。僕の乗っている船【暁皇】は宇宙貿易船であり、桐ノ院コンツェルンの中枢基地だ。傘下に多くの宇宙船を抱えていたが、その中でも一番大きく、設備が整っている。地上にいれば誘拐やらテロやらの危険にさらされる事の多い桐ノ院家の直系としては、【暁皇】にいるのが一番安全であったから、家族は皆ここで暮らしており、贅沢な生活を過ごし続けている。この船はほとんど惑星に対する衛星ほどの大きさをしているから、中では我々の家族の他にも何千人という人間が住んでおり、様々な仕事をし、生活を楽しんでいた。
僕の名前は桐ノ院圭。この船のオーナー船長、桐ノ院胤充の長男であり、唯一の息子だ。
下に妹が一人いるが、僕がいずれこの桐ノ院コンツェルンを率いる事が小さい時から決まっていたから、幼いときから多くのカリキュラムが組まれ、厳しく教育されていた。父だけでなく、母も僕を妹のように甘えさせてくれる事は少なかったが、それは僕が次代を担う人間として期待されているのだと思い、がんばって認められるよてもらえるようにと、一生懸命に様々なカリキュラムをこなしていた。
それでも時折は、笑いながら無造作に父や母に甘える小夜子をうらやましく思うこともあった。けれどすでに無邪気に甘えるには僕はもう賢しくなりすぎていた。幼い頃は、母にも何も考えずにしがみついて甘えていたこともあったはずなのに、今の僕には小さな大人として振舞う事しか出来なかった。
そんな不器用なプライドに鎧われた僕を、まるで自分の子供のようにして慈しんで接してくれていたのは、昨年ほぼ完全に引退して悠々自適の生活をしている祖父の秘書兼執事をしていた伊沢で、彼は僕にカリキュラムにない様々なこと――音楽、絵画、虫の話やむかしの童謡など宇宙ではまるで役に立たない、しかし心を豊かにしてくれる面白い事ばかり――を教えてくれていた。
僕が大人になった今こうして無味乾燥な人間にならずに済んだのは、彼のお陰なのだと思っている。
地平線を見渡すように、まるで先々の未来までが決まっているような生活の中で、忘れる事の出来ない事件と出会いが起こったのは僕が八歳の時のことだった。
銀河標準暦821年五の月十八日。
【暁皇】は惑星那由他へと到着した。ここは最近汎同盟に再加入して来た惑星で、活気にあふれた商業惑星だ。今回、【暁皇】は大統領の就任式典に招かれて投錨することになったのだ。一週間ほどの滞在であり、この星は治安がいい事ということで、僕も初めて惑星に降り立つ事が許されたのだ。
生まれて初めてのことに僕はきっと浮かれていたのだと思う。だから、今までしたことのなかった事――母の部屋へ飛び込んで、これから地上へ出発する事――を告げようとしたのだ。
しかし、そこで僕は一番聞きたくない言葉を聞くはめになってしまった。
「なんですって!わたくしが圭さんをないがしろにしているですって?!」
しゃべっている相手は父だったのだろうが、僕には母の声だけが聞こえた。
「たしかに圭さんは、おなかを痛めていない息子ですけれど、亡くなられた芙美子お姉様のたった一人の忘れ形見で、わたくしがこの手で育ててきたのですわよ?!桐ノ院家の大事な跡取りとして、小夜子のこと以上に心を砕いてきているのは、あなたもご存知でいらっしゃるはずでしょう?!それを、ないがしろにしているだなどと!わたくしは、自分の責任は心得ておりますわ。圭さんの母親としての務めは、誠心誠意果たしております」
その瞬間に、僕の中で燦子母上への思慕と愛情への渇望が、消えてしまうのをまざまざと感じていた。
すっかり度を失った僕だったが、頭の隅では、言い争っている両親は息子が聞いていたことを知るのは気まずいと思うだろうとか、気づかれて言い訳でもされたらさらにつらい事になるだろうとか考えていて、来た時とはまったく逆に、静かに音を立てずにこっそりと母の部屋を逃げ出していった。
「ああ、坊ちゃま。そろそろ地上へ皆さんが降りられますよ」
無意識のうちに自分の部屋へ戻る通路を歩いていた僕は、その途中で、息を切らしながら探していたらしいハツと出会った。
「もうそんな時間?」
まだ時間はあると思っていたのに。
「伊沢さんは、ご用があって坊ちゃまとご一緒できいそうなんですよ。ハツがご一緒しますから、坊ちゃまをゃんとお守り出来ますからね」
ちゃんとわたしも身用の武器も持ってますし、得意そうにハツが笑った。
ハツはかなり前に亡くなった祖母の小間使いをしていた女性だ。僕の小さい頃には僕の世話係をしてくれていて、なにくれとなく僕を甘やかしてくれた。その頃、節くれだったハツの手から手渡されるおやつの数々は僕の一番の楽しみだった。
しかし、大きくなってきた僕にとってハツの甘やかしは、未だに僕を小さな子供のように扱っていて、僕の世話係が伊沢に移った今となっては、わずらわしいばかりのものだ。僕がもう充分大きいのだと暗にほのめかし、伊沢一人がついていれば充分だと言ってみても、伊沢を押しのけるようにして僕の世話を焼きたがる。
どうやって、今回伊沢を僕の引率から外すことが出来たのかはわからなかったが、このぶんでは僕が地上で見たいと思って伊沢と計画し、面白そうだと思っていた様々な場所への見学は出来ないことだろう。僕はこっそりとため息を押し殺し、ハツのそばへ行った。
「ええ、それでは行きましょう」
【暁皇】は大きすぎる為にそのまま惑星上へ降りる事は出来ない。衛星軌道上にある係留場に停泊する事になる。地上に降りたいものは、搭載艇を使ってここから地上へと降りていくことになっている。僕が搭載艇の乗船口へと歩き出すと、ハツは僕の手をつかまえに来た。
「ハツ、僕はもう小さな子供ではないのだから、手をつながなくてもいいです」
「いいえ、この先は人が大勢なんですよ。坊ちゃまが荒っぽい男たちに突き飛ばされなどしたら、たいへんでございますから」
僕はまた一つため息を押し殺した。僕はすでにハツと同じくらいの身長を持っているというのに。
「坊ちゃま、どこに行きましょうね。動物園ですか?それとも遊園地?」
「ハツ。僕は市場と商工会議所に行きたいです」
「そんな、だめでございます!そんな場所で子供がうろうろしていたら、どんな危険なやつらが出てくるか分かりません。坊ちゃまをお連れするわけには参りませんよ!」
「大丈夫です。僕はナビをつけていますから。迷子になったりしてもどこに自分がいるかは分かるし、もし万一誘拐などされても居場所はすぐに分かるのですから。それに、どういう人間が危ないか、充分にシュミレートしています。危険な場所には近寄らないですし」
「また伊沢さんの入れ知恵でございますか。まったくあの人と来たら・・・・・。坊ちゃまがどんなに大切なお方なのかわかっていないのだから・・・・・」
ハツはぶつぶつと伊沢に対する不満を続け、僕の言うことに耳をかそうともしなかった。そうして僕はまるでまだ小さい子供のように、ハツに手を掴まれたままで搭載艇に乗り込むハメになり、かなり周囲に気まずい思いをした。
搭載艇は地上へと降りる用事のある者たちを乗り込ませて発進していき、宇宙空間から大気のある層へ突入して滑る様にゆっくりと地上へと近づいていく。それにつれて、僕の中では再び初めて地上へと降りる事への期待と興奮が湧き上がってくるのを感じていた。
僕は星がまたたくという事を、この惑星の大気に突入するまで僕は知らなかった。もちろん、知識としては知っていたが、僕が見る星は宇宙からのものばかりだったから、まったく地図の記号のように厳然とそこにあるものであり、なんの情緒もそこに入り込む余地はなかった。人の話や小説の中に語られる星は、僕が知っているものとはまったく別物のように感じられていたが、今ここで見ている実物は背景ホログラムや記録映像ともまた異なっていて、確かに僕の中の何かに訴えるものがあるように思えた。
星のきらめきに魅了されているうちに、搭載艇はやがてきれいな星の輝く夜の部分の飛行から、昼になっている大陸へと移動して行き、辺り一面豪華な朝焼け色の光の競演に包まれながらタペストリーのような大地が広がっていく光景を僕らに見せていき、徐々に下降していくにつれて、様々な建物が立ち並ぶ地上が目の前に近づいてくる。搭載艇は惑星那由他の首都「須弥」に到着した。
――惑星「那由他」 重力1.016 酸素量 0.998
首都「須弥」――
現地時間 13:08
地球とほぼ同質の生活環境。宇宙船の内部も地球の環境と同等に整えられているから、船からそのまま下りてもからだはさほど違和感を感じない。僕たちは手続き上の検疫を受け、税関を通り、いよいよこの星へと足を踏み入れた。
しかし、見る事と知る事とはまったく違うものだ。僕は始めて地上に降りて、他の人々が気にも留めていないいろいろなことがらに次々と魅了されていった。建物群に色とりどりの屋根やひさしがあることや、強い風が吹くとそこに砂が混じっていたりすること。木々の陰がくっきりと一方に付いている事、街の中に様々な騒音が響いている事・・・・・。
それらは宇宙船の中では味わう事が出来ないものだ。地上に降りるという事は、こういうことなのだ!
「坊ちゃま。行きましょうか?」
ハツが僕を促した。また手をつなごうとするのを拒んで、僕は歩き出す。ハツは僕が街の有様に怯えて呆然としていたと思ったらしい。
僕はただ、伊沢が前に言っていた『知識で知る事と自分の五感で味わう事の違い』を肌で感じていて、地上で初めてのあらゆる事象に感動していただけなのだが。
「はじめにどこへ行きましょうかねぇ。ここの動物園は大きいそうですよ」
「・・・・・ハツ。僕は動物園には興味がありません。博物館へ行きましょう」
「そうなんでございますか?それじゃあ、そちらに・・・・・。さて、どうやって行くのだったかしらね」
ハツがナビをいじり始めた。初めての僕を引率するというのなら、事前にある程度行きそうな施設の場所くらいは把握していてもいいと思うが。
「こちらのチューブに乗るはずです」
僕はここへ来る前の勉強の一環として、すでに街の主な施設の場所は地図上で調べて記憶してある。しかしハツはナビ(携帯用ナビゲーション&通信システム)を見て自分で場所を確認して、それからやっと僕の言葉どおりに一緒にチューブへと歩き始めた。
チューブというのは、都市のあらゆる方向に伸びている公共交通手段で、その語源は古く『オールド・ホーム・テラ』(地球)で使われていた交通機関の名前を使っているのだという。卵形のポッドに乗ると一人、または数人を一緒にして目的地まで運んでくれるその乗り物は、汎同盟内に属しているほとんどの惑星ではごく一般的に使われている。
僕はポッドの中から街の中の多種多様な文化が平和に混在していることに感心し、変化していく街の風景を楽しんでいたが、一緒に乗ったハツにはそう思えなかったらしく、この星の住民についての非能率なことがらや礼儀の悪さなど不平不満を僕に言い募っていた。そうやって彼女は自分たちが暮らしている【暁皇】のよさを僕に分からせようとしていたのだろうが、僕にとってはハツの狭量な偏見を知って、昔は好意を持っていた人間への失望を味わわされているだけだった。
博物館に入り、見た事のない不思議な物で溢れているその空間を、もし自分独りだったら楽しめたことだろう。あるいは気の会う人間と楽しく意見を交わしあいながらだったら・・・・・。しかし、そこに書いてある説明をいちいち読み上げて聞かせようとするハツといっしょでは、神経が疲れて滅入ってくる。彼女はごく善良な人間で、(彼女にとってはまだ幼い)僕に良かれと思ってそうしてくれているのだろうが、僕の興味は説明を見てわかるものではなく、そのときそのときに人間がどうかかわっていたかの背景が面白いのだ。
「・・・・・ハツ。そろそろ戻ります」
「ええ、ええ。それがよろしゅうございます。こんな汚くてうるさい場所坊ちゃまにはふさわしくありませんものね。早く戻りましょう」
帰還する刻限にはまだ3時間近くあったが、これ以上ハツに気を使いながらの見物は願い下げだった。ハツは僕が腹を立てていることにまったく気がついておらず、早足で行く僕のあとにいそいそとついてきた。
博物館から出て、またチューブの乗り場へ行こうと向かっていたら、どっと大勢の人たちの声が襲い掛かってきた。どこからともなく現れる人々の群れ・・・・・。群集は次第に広場へと集まっていく。
「内乱でも起こったのでございましょうかね?」
ハツが怯えた声をあげた。
「これは、大統領就任に反対するデモですね」
昨日僕が調べた時、今日ここで小さなものだがデモが行われる事を公示してあったのを思い出した。しかしあくまで小規模なもののはずで、デモというものがこんなに人が集まるものだと、そして人々を興奮させるものだという事を僕はまったく知らなかった。
「坊ちゃま、早く!」
うろたえたハツは僕の手を掴み、急いでチューブの入り口へ入ろうとした。しかしそれは逆にデモに参加しようとする人の波に巻き込まれる行為だった。数人の男たちが前を行くものたちに追いつこうとして僕らにぶつかり、僕とハツは左右に引き離されてしまった。
そのとき僕の手首にはめていたナビが下に落ちてしまい、アルミプラスチックのバンドがカラカラと軽い音を立てて、遠くに跳ね飛ばされていった。それを誰かにまた蹴り飛ばされてあわてて探し回り、ようやく拾い上げてハツの立っている場所を振り返って見てみると、僕を探しにどこかへ動いてしまったらしく、その姿が消えていた。周囲を見回しても彼女はどこにもいない。
急いでナビを開いてみたが、蹴り飛ばされた時にどこかが故障したらしくうまく繋がらない。これではハツがどこにいるのか分からず、こちらからは連絡が取れない。その上、その場にじっとしていてもハツが現れないところをみると、向こうのナビにこちらの信号を送って位置を知らせる機能の方もだめになっているらしい・・・・・。つまり、完全な迷子。
ここで僕が感じなければいけないのは、孤独とか不安とかでなければならないはずだったが、今感じているものは何も我慢しなくていいという自由さと楽々と息が出来る開放感だった。
―― そうだ。今ここでは、周りにいる誰のことも僕は知らない。周りにいる誰も僕を知るものはいないのだ。――
僕はすばやく考えをめぐらす。門限にはあと三時間。ここの日没まではあと二時間半。船まで帰るのに必要な時間は30分。
ハツが船に今すぐ連絡を取っていれば、本船のメインコンピューターが僕の体内にある発信チップの場所を探し出し、僕の居場所を瞬時に教えることだろう。僕が桐院家の一員である為に、誘拐を想定して付けられているものだ。しかしこれは本当に非常用で、たいていはナビから探し出すことを第一とする。発信チップを付けていること自体が、最重要機密なのだから。しかし今ナビは不可抗力で故障している・・・・・。
自分のミスで僕とはぐれたハツは本当に土壇場にならなければ、僕の両親と連絡を取ることはないだろう。自分だけの力でなんとかしたがる女性だから。それに加えて、絶対に弱みを握られたくない伊沢への意地も手伝って。
僕が護身用の武器を持っていることも、その扱いに慣れていることも彼女は知っている。・・・・・最も、その腕前を信用してくれているかどうかは別の話となるが。
――2時間だけ、僕の好きなように使ってもいいのではないか?――
僕の中でそんなささやきが聴こえる。平素の素直で賢くて礼儀正しい僕であれば考えもしないことだ。しかし・・・・・そうだ、頭の中でいつも空想していたようにごく普通の少年として、道草を食ってから家に帰ることにしよう!
僕は歩き出す。デモから離れ、あちこちの店を覗き、あまりきょろきょろとしないようにしながら急ぎ足で、目的地がそちらにあるような振りをして。
そうして目に入ってくる街の風景は、船の中のように無駄をはぶき、計画性を持った整然とした美しさではなく、雑然としていて、しかも活気を帯びた生気を振りまいていて、街が刻一刻と変化し続けているのがよくわかる。
やがて僕は商業地域から住宅地へと足を踏み入れていたのに気がついた。そこはどうやらかなりの高級住宅地らしく、沢山の植物や塀に区切られたユニット(ああ、ここでは屋敷というべきなのだろうか)が整然と並んでいる。そこの一軒から聞こえてきたのは、以外にも古き地球のアジア辺境地域の歌。ニッポンの童謡だった。子供たちが歌っている・・・・・?
「夕焼け小焼けの赤とんぼ。
おわれて見たのはいつの日か。
山の畑の桑の実を
小籠につんだはまぼろしか」
男の子らしい2人の声が聞こえる。僕は声に誘われるままにそちらへと歩き出し、大人では入れない生垣の隙間からこっそりと中を覗いた。
そのときだった。
「だあれ?そこにいるの」
ふっくらとやさしい声が僕に声を掛けてきた。
・・・・・ニッポン語だ!