う つ せ み
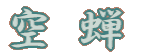
レースのカーテン越しに揺れる日差しが目の裏にまぶしい。
どうやら予定よりもいささか寝過ごしたようだが、気分はすっきりとしている。
僕はベッドの中でぐいっと背伸びをした。
「―――いい夢を見た」
先ほどまでみていた夢を、楽しく反芻した。
内容はほとんど覚えていない。けれど、夢の中で僕は実に幸福な時を過ごしていたという感覚だけは、はっきりと残っている。
「悠季?」
隣りに眠っているはずの彼に触りたくて手を伸ばしたが、触れたのはひんやりと冷たいシーツの感触だった。
ああ、彼は今日は留守でしたね。
演奏旅行ツアー中で、ここに帰って来るのは、明日。
思い出したスケジュールにがっかりしたが、せめてかれの残り香で慰めを得ようと寝具に顔を押しあてた。
けれど残念なことに、きちょうめんな悠季は出かける前にシーツや枕カバーのたぐいを全て洗濯してから出かけたらしく、洗剤と柔軟剤の香りしかしない。
未練がましくため息を一つついてから、起き上がってシャワーを浴びに行った。
悠季が帰って来るまでの時間を過ごすための活力を得るために。
熱いシャワーと冷たいシャワーを交互に浴びてすっきりしたところで、夏用の肌触りのよいシャツとトラウザー、出かけるときに羽織るジャケットを手にして階下へと降りた。
今日の予定は、午前中に宅島がやってきてこれからの打ち合わせをし、その後MHKの練習場へ出かけて幾つかの雑用をこなす。
今夜はフジミの練習はない日なので、明日帰って来る悠季のためにいささか凝った料理の仕込みをすることにしようか。
在り合わせのもので朝食を済ませてから音楽室に入ると、どこかに違和感を感じた。
何かがおかしい。
いつもの見慣れた部屋とはどこか違っている。しかしそれが何なのかが分からなかった。
自分が感じているものの正体が掴めないうちに、呼び鈴が鳴った。宅島がやってきたのだ。仕方ない。考え事はあとにしよう。
「お早うございます、ボス」
ほがらかな声で入ってきた宅島には、部屋の中に何も異常を感じていないらしかった。
「さっそくですが、来月のアメリカツアーについて・・・・・」
打ち合わせは順調に進み、時間になったところで僕の車でMHKの事務局に向かう事になった。
間もなくMHKに到着するというところで、ふとこの間から言うつもりだったことを思い出した。
悠季との共演について、早めにスケジュールをおさえておいてもらうつもりだったのだ。
「宅島。来年の春、悠季との協演について早めに予定をおさえておいてもらいたい。事務局から獲ったソリストの指名権が使えるはずです」
「はあ、指名権は分かっていますが、その『ゆうき』っていうソリストは誰ですか?事務局にきちんと通る人物じゃないと申し込めませんが」
「冗談はやめたまえ」
僕は思いきり眉をしかめた。仕事の最中にこの悪ふざけはたちが悪すぎる。
「冗談って・・・・・。俺は一度もその人のことを聞いたことがないんだが」
「・・・・・何を言っている?」
「だから、誰なのか知らないんだって」
「ばかなことを!僕と一緒に住んでいる守村悠季のことだ。それでも知らないというつもりか!?」
「一緒にって言ったって、あそこにはボス一人で住んでいるはずだろう?それとも最近誰かを連れ込んだのか!?」
なんというふざけたことを!!
僕は目もくらむような怒りに言葉も出なくなった。
それ以上宅島と話しているとどんな罵詈雑言を口にしてしまうか分からない。
車が練習場に到着したところで、さっさとドアを開けて出ると、宅島を置いて先に事務局へと入っていった。
「やあ、殿下」
入ってすぐに声がかけられて振り向くと、飯田君だった。どうやら彼はゲスト指揮者のAプログラムに出演する予定で、今日はそのリハーサルらしい。
「今日の殿下はリハーサルじゃあない日だろう?それとも事務局長に呼び出しでもくったのかい?こき使うからなぁ、あのタヌキは」
相変わらず口の悪い。
「お早うっす!」
背後からまた声がかかった。
「よう、先輩。ペーペーは一番乗りするんじゃなかったのか?」
「もう一番下じゃないから、二番乗りっす。コンは今回のプログラムは振らないはずですよね?突発で入ったんっすか?」
「ほら、こいつも事務局長のことをよく知ってる」
飯田が大笑いして言った。
「いえ。僕の用事は呼び出しではありません。・・・・・ところで、君たちに聞きたいのですが、『守村悠季』ことですが」
「もりむら、ゆうき?・・・・・って、誰だ?」
飯田が首をかしげた。
「先輩、知ってるか?」
「さあ?」
二人の顔には僕をからかっている様子はまったくない。ごく普通の態度で、僕の言葉に戸惑っている様子だった。
「・・・・・覚えていない、のですか?」
「聞いた事のない名前だな。あ、もしかしてフジミの団員か?最近何人か入ったって聞いたから、その中の一人か?」
「何を言っているのですか!何回も協演したではありませんか。フジミのコンマスで、MHKで、僕の指揮で協奏曲をやっている!」
「えーと・・・・・コン?フジミのコンマスは市川さんっすよ。その前は俺でした。石田さんに頼まれて、三年ほどやって、MHKに入って忙しくなったから市川さんに替わってもらったんですから。それに、フジミにそんな人は入っていないはずで」
「いい加減にしたまえ!」
僕は五十嵐をどなりつけた。
これ以上、馬鹿馬鹿しいたわごとは聞きたくなかった。
僕は腹の中に熱い塊が湧きあがって来るのを感じていた。どうして悠季をよく知っているはずの人間たちが、こんなたちの悪い嘘をつくのか。
「一昨年、僕の指揮で悠季がブラームスのバイオリンコンチェルトを演奏しているのを覚えていないと言うのですか?!」
「おい殿下。何か勘違いしてないか?一昨年ブラームスをやった時のソリストはムターだったぜ。ちゃんと覚えてる。事務局に行って、過去の記録を見れば分かる筈だぞ」
そうか。それがあった。記録ならばちゃんと『守村悠季』の名前が出ているはずだ。
僕は心配そうな二人を残して急いで事務局へと入り、ここ数年の記録を出してもらった。
悠季とMHKが競演したのは、これまで三回。そのうち二回は僕との共演で、一回はゲスト指揮者との共演だった。
その日時は全て記憶している。
だが。
「・・・・・ない」
悠季と共演していたはずの二回のコンサートには、違うソリストの名前が書かれており、ゲスト指揮者のところのソリストにも他の名前が書かれていた。
記憶の間違いではないのかと、数年分を全てを見直したがその中のどこにもソリスト『守村悠季』の名前は書いてなかったのだ!
「・・・・・どういうことだ?」
僕をからかうための冗談なのだと信じていたのに。だが、僕をからかうためだけにここまで念の入ったしかけをするはずもない。
「いったいこれはどういうことだ!?」
これで何回この疑問を口にしたことだろう。
熱い怒りはいつの間にか腹の中の冷たい氷の塊と化していった。何が起こったというのだろう。『守村悠季』は僕の頭の中だけの人間だとでもいうのだろうか!?
じわじわと黒いしみのように心の中を恐怖が噛んでいくようだった。
しかし、悠季が、守村悠季が存在していないなど、絶対に認められないことだった!
「・・・・・そうだ。石田くんなら知っているはずだ!」
フジミの世話人で、悠季の身元引受人を引き受けたこともある彼なら、『守村悠季』を知らないなどとは言わないだろう。
僕は急いで事務局を飛び出した。
宅島が何か叫んでいたようだったが全て無視し、やってきたタクシーを止めて乗り込むと、そのまま富士見町へと引き返した。

