遁走曲
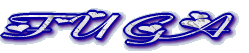
あたしは何のとりえもないごく平凡なOLだ。せいぜい子供の頃にバイオリンを習っていたってことがあるくらいの。
もっとも友人にはこんなことを言ったことはないけれど。
子どもの頃のあたしにとって、バイオリンは本当に大切な宝物だった。
幼稚園のときに出会ったバイオリンに夢中になり、次々に曲をマスターし、コンクールにも出場して入賞もした。
父や母はあたしのことをたいそう褒めてくれて、とても得意だった。
あたしの将来の夢はバイオリニストになることであり、それは夢というよりも確定した現実のはずだった。
でも、年を追うごとに見えてくる厳しい真実があたしの夢を打ち砕く。
本物のバイオリニストになれるような優秀な子供は、すでに難しいソナタやコンチェルトをすらすらと弾きこなしていたのだ。
でもあたしが入賞して有頂天になっていたコンクールは、普段コンクールに入賞できないような子どもたちのために与えられた程度が低いもので、音大に進むような才能のある子は見向きもしないものだったのだということを知った。
そんなことに気がついてしまうと、もう今までのようにバイオリンを弾くことが出来なくなってしまっていた。
あたしが今までやってきた努力やがんばりを両親は惜しがっていて、日常の楽しみとして弾くことを勧めたけれど、幼い子どものわがままな思考や視野の狭さと潔癖さとはあいまいな妥協を許さない。
宝物だったバイオリンは惜しげもなく手放し、大切に集めていた楽譜やCDとあこがれたバイオリニストのコンサートを聞きに行ったときに手に入れたパンフレットなどは全部捨てた。
自分の目につくところからは全て、バイオリンの気配すら許さなかった。
そうして高校も大学も音楽とはまったく縁のないところへと進み、就職した。その頃知り合った友人たちはあたしがバイオリンを弾いていたことなどまったく知らない。あたしも忘れることにした。
けれど、心の奥底に住み続けているバイオリンを愛していた幼い子どもは、あたしの無関心さをなじり今もあきらめきれないと泣いている。
だからなのだろう。卒業後に就職が決まったのは大手の音楽関係の企業だった。胸の中のくすぶりを少しでも鎮めるために入ったようなものなのかもしれない。けれど、中に入れば理想と現実とは違っていた。
子供音楽教室やイベント関係の業種を希望していたのだけど、配属されたのは皮肉にも一番やりたくない部署。楽器の販売、それもバイオリンがメインの部署だったのだ。
店なら利益を出すためにバイオリンを売らなければならない。当然のことだ。
けれど、とにかく来た客にはたとえそれがどんなひどい楽器でも、客が欲しいというのなら売らなければならない、というのはあたしにはつらいことだった。
たとえば。
バイオリンの売り場の中央にはつやつやとしたニスを塗られた綺麗なバイオリンが派手なスポットライトを浴びてディスプレイされている。たおやかなフォルム。いかにも素敵な音を奏でそうな。
何も知らなくて買いに来たのなら、まず手に取って見たくなるような一番目立つ場所に置かれたバイオリン。
けれどあたしは知っている。そのバイオリンが形はいいけれど、音は悪いのだということを。
値段はお手ごろ。イタリア製で、大きな工房の作品としては、むしろ安いくらい。弾いてみれば弾く人にはそれなりに聞こえる。
はじめのうちは。
けれど弾いている者も次第に耳が肥えてくれば自分が弾いているバイオリンの音色が鈍くて、弾いている本人はそれなりでも周りには良い音ではないことに気がつくだろう。すぐそばで聞くならいいけれど、透明感のある響く音ではないのだ。そうなればこのバイオリンは飽きられて放置されて、おそらく次のバイオリンを購入するんじゃないだろうか。
これを仕入れた担当者はそのことを知っているから、早めに売ろうと思って安値に設定したのかもしれなかった。
初めてバイオリンを買うのだと言って店を訪れ、このバイオリンに目をつけたなんていうカモされやすそうなタイプの客には、あれこれと問題点を指摘して鼻白ませ、挙句の果てに何買わずに帰らせてしまった。おかげでフロアチーフにはさんざんに文句を言われた。
「あんたね、バイオリンを買いに来た客をそのまま返すなんて何やってるのよ!選ぶのは客なんだから、こっちは買いたいという客の望みを叶えればいいだけなんだから。わかってる?買ってもらわなきゃウチの店はなりたたないの」
そのとおり。店の道理だ。楽器店なのだから、商品は売らなければならない。けれど、客がそのうちに嫌気が出るだろう楽器を売るのは、バイオリンがあまりにもかわいそうに思えて、売ることが出来ないのだ。
しばらくは我慢して勤めていた。けれどどうしても我慢できなくなってしまっていた。そして・・・・・。
もう、この店をやめてしまおうか。
そんな思いが頭の片隅にちらちらと浮かび続ける。
それでもせっかく就職できたのだからと、半年は我慢した。せめてと転属願いを出したけれど、聞き入れてはもらえなかった。
そんなとき、いつものように帰宅途中、乗換駅でそれまでは気にも留めなかった高速バスの乗り場の看板に目か留まった。
乗ってしまえ!
あたしは発作的にそのままバスに乗ってしまっていた。運転手さんに代金を払って席に着く。どうやらこんな飛び込みの客も時々いるらしい。
うんざりする職場に行かないというだけでなんと息が楽なことか。
週末なんだからあさっての朝までに家に帰ればいい。もし気が向かなければ会社に電話をして休暇をとればいい。
そう決めたら更に気が楽になった。
行き先は仙台。
だということは、乗ってから気がついた。
翌朝早くにバスは駅前に到着した。
とりあえず目的もなく街中をぶらぶらと歩いて、それからこの先のことを考えよう。
けれど、誰も知らない場所に行こうと思ったはずなのに、どこか見覚えがある。
なんでだろう?
思い返してみるとここは叔母が住んでいる場所だということに気がついた。
両親とバイオリンのことで気まずい関係になったあと、他の親戚関係にも疎遠になっていたけど、何回か訪れていたことがあったのを今頃思い出していた。
久しぶりに叔母さんの顔を見に行ってみるのもいいかもしれない。さばさばした気性で、早くに夫を亡くして、一人で悠々自適に過ごしている人だ。子供の頃はよくかわいがってくれていた。
そんなことを考えながら歩いていって、ふと気がつくとぱらぱらと雨が降ってきていた。それほどの降りではないけれど、このまま雨の中を歩いているのも嫌だからどこか喫茶店でもないかときょろきょろしながら歩いていって、小さな路地に入り込んでいた。
それほど新しくもないビルの1階にアンティークを並べた飾り窓がある。喫茶店かと思って近づいていくと、そこはバイオリン工房だった。
なんでこんなところまで来てバイオリンなのよ!
自分で自分に突っ込みを入れて、もと来た道に引き返そうと思ったのだけれど、中の雰囲気に引き寄せられるように、ついふらふらとドアに手をかけた。
からんからんと軽やかなドアベルが鳴っているのを聞きながら店の中へと入っていった。
入ってすぐの正面が大きな机が置いてあって作業スペースになっているのが珍しかった。奥の方には駒や弦などの部品のついていないバイオリンやビオラが壁にずらりと並べられていた。この工房の人の作品なのだろうか。
そして、棚にはバイオリン作りや調整に必要な道具が整然と並んでいた。静かでバイオリン特有の香りがしていて、とても心がざわついた。
つややかなニスを塗られた何丁かの真新しそうなバイオリンが飾られていたが、ニスが劣化するような明るい光などは当てられていない。ここにあるどのバイオリンも大切にされているのだと思えた。
ここだったら、苦々しい思いをしながらバイオリンを売るようなことはないのだろう。もしここが職場だったら、またバイオリンと向き合えるかもしれない。そう思えるような心地よさをこの店は持っていた。
「ごめんください」
あたしは声をかけたのだけど、どうやら無用心にもここの店主は店を閉めずに出かけているらしい。しかたなく店を出た。
『事務員を募集中』 音海バイオリン工房
窓にそんな張り紙がしてあった。音の海なんてしゃれた名前。
そんなことを思いながら、もと来た道を駅に向かって歩き出していた。また来てみたいけどもうここには来ることはないだろうけどなぁと少し寂しく思いながら。
雨はもうやんでいた。
そんなセンチメンタルなことを考えていたときもありました。
今のあたしは仙台に住んでいる。
本当に縁とは意外なものだと思う。
あの時、工房を出て歩いていると思いがけずばったりと叔母に出会ってしまったのだ。
聞いてみると意外にもこの近所に住んでいることが分かって、そのまま近くの居酒屋に食事と飲みに引っ張って行かれた。
そして、アルコールのおかげもあって今の自分の状況や不満や鬱屈を全部吐き出してしまい、あげく叔母の紹介でこの地に新たな職場を紹介してもらうことになったのだ。
それがなんと、音海バイオリン工房の事務員だった。
店長で工房長は音海さんという珍しい名前で、工房の名前は奇をてらったものではなく苗字そのままだった。
彼は若手のバイオリン作家としてそこそこ名が売れてきているそうで、今までは一人で工房を回していたけれど、客への対応に時間をとられるのがわずらわしくなっていたのだそう。
知らなかったけれど仙台では音楽活動が盛んだそうで、近くには音楽教室がいくつもあり、その中には必ずと言っていいほどバイオリン教室もある。バイオリンを習っていると当然バイオリンの修理やメンテナンスの需要があるので、そちらの仕事も増えているそうだ。
仕事中に客が来ると中断しなければならなくなるし、にかわなど途中で手を止めることができないものもあるから、自分の代わりに対応してもらう人間が欲しかったらしい。
そしてあたしは一度東京に戻ってすっきりした気分で職場に退職願を出し、1ヵ月後にはまた仙台に戻ってきた。
住まいは叔母が持っているアパートの空いている部屋に住まわせてもらった。ちょうど転勤で出て行った人がいたそうで、安い家賃のかわりに壁や床の補修をしないままで入った。ちょっと好みじゃない壁紙はホームセンターに行って購入してきた素人でも貼れる壁紙を貼って満足できるものになったし、床の傷は同じく補修剤でうまく綺麗にできた。
そしていよいよ新しい職場に入ったのだけど、確かにこの店長なら早めに事務が出来る人が欲しくなったはずだと知った。仕事馬鹿というか、バイオリンに触っているのが無常の楽しみらしくて、いったん仕事に入るとお客が来てもなかなか気がつかないことがあるのだ。初めて中に入ったとき、店の表に工房があるのは珍しいと思ったけど、あれは客が来たときにすぐに分かるからということらしかった。
だから店員としてあたしが入ってすぐに店の中は模様替えがされて、仕事場であるテーブルは奥のほうへと移されていた。確かに鑿や鉋が客の手に触れられるところにあるのは危ないから。
店にある品物を把握して、常連さんや近くの音楽教室の事務員さんなど、色々な人と知り合いになっていって、この街に受け入れられてきているような気がしている。けれど、未だに自分が昔バイオリンを弾いていたことは、誰にも言っていない。どうしても口が重くなってしまうのだ。
そしてもう一つ。東京から持ってきた荷物の中に、バイオリンが入っていることも。
あの、鈍重な音をしたバイオリンがどうなるのか心配だった。見た目だけで買われた後ぞんざいに扱われてしまうかもしれないとか、棚ざらしのままでいつまでも照明のきつい場所に置かれたままかもしれないなんて考えてしまうことが嫌で、退社する直前に衝動的に社員割引で買ってしまい、こっちに持ってきてしまった。
でも、こちらに来てもケースに入れてクローゼットにしまったままだ。本当に自己満足でしかないのだ。