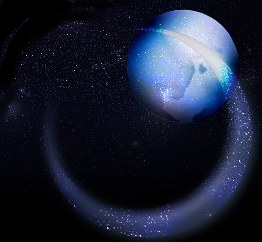![]()
「悠季、そろそろ起きませんか」
「・・・・・んーん」
僕が声をかけてもぐっすりと眠っていて目覚めない。
こんなふうに無防備に眠っている彼の、毛布でくるまれていてもちらりと出ているくっきりと腱が浮き出ているくるぶしや、毛布を盛り上げているほっそりとした腰のあたりのラインを眺めていると、何やら手を出したくなってしまうではないか。
昨夜、彼と深夜まで愛し合ったばかりだというのに。
おそらくこんなに深く眠ってしまって起きられないのは、昨夜彼が失神するまで付き合わせたせいで疲れが残っているためもあるのだろう。
まぶたに薄青い陰を刷いているのも、おそらくそのせいなのだ。
悠季はロン・ティボー国際バイオリンコンクールで優勝した。
そうなるだろうと僕が確信していたとおりに。
が、優勝の影響は大きかった。
予想はしていたが、授賞式の後にありとあらゆる媒体からインタビューや取材の申し込みが入り、あちこちから演奏の依頼が続いた。
他にも多くの人たちからの電話がひっきりなしにかかってきていた。
それは家族郷里の友人知人、フジミのひとびとからも続々とかかり、海外からもブリリアントオケで共演した者たちから次々とかかってきた。
どこかからかこの家の電話番号を知ったのか、中には今回の受賞とはまったく関係のないやからまで。
そのせいで家の電話が鳴りっぱなしだったのだ。
インタビューの申し込みや取材には全て宅島を間に挟んで選別させた。
そうしなければ慣れない悠季にとってどこを受けるか考えるだけで多大な負担がかかっただろうし、人見知りをするたちだと言っている彼にとっては数多く応対するのはきついことだったはずだ。
想定していた以上の反響で、悠季はすっかり疲労困憊状態になってしまっていた。
そんな大騒ぎもこのところようやく沈静してきた。
また来年一月の演奏会に向けて練習を開始することになるだろうが、今はようやくバイオリニスト守村悠季という立場から解放されて、恋人である僕の悠季に戻ってくれた。
そこで僕たちは疲れをとるために数日間の休暇を得て、静かな隠れ宿に出向くことにしたのだ。
残念ながら僕たちの住んでいる家にいては、いつまた電話や不意の来客が現れるか分からなかったので。
宿は伊沢に頼んで予約してもらったものだったが、静かで誰にも邪魔されず、二人で温泉に入ったところで今まで肩に力が入っていることにようやく気がついて苦笑しあったものだ。
さりげないもてなしと美味しい食事。
しんと静かな離れで、二人で抱き合ってやすんだのだが、そのまま盛り上がってしまったのだ。
今までの鬱憤を晴らすかのように、夢中で悠季を抱いて、悠季も情熱的に応えてくれて・・・・・。
―――― ここに、呼びかけても起きない悠季の姿があるわけである。
朝食を運んでもらうのはこちらからの電話がかかってからということになっている。
客の好きなように過ごさせてくれるというこの宿のサービスは、絶好の状況をうみだしている。。
誰にも気兼ねはいらないという状況は、僕の理性の鍵を外すものになる。
性懲りもない僕は、悠季を僕だけのものだと感じたくて悠季に甘えてしまうことになる。
「悠季、起きないならこのまま始めてもいいのですか?」
僕は耳元にささやきかけたが悠季からの返事はない。
どうやらまだ眠りは深いようだ。
「起きないならこのまま続けても・・・・・いいですね?」
「・・・・・んー・・・・・いいよー」
返事をしたわけではないだろう。
僕の言葉に反射的に応えただけなのだ。
しかしいたずらな手を抑えることが出来なかった僕は、都合のよいように解釈をすることにした。
以前悠季は、『君は眠っているボクを起こすのが好きだよね』と、苦笑交じりに言った事がある。
確かにそのとおりだ。
普段ははじらいが悠季の理性を縛るせいか、なかなか素直に快楽を愉しむ姿を見せてくれない彼が、寝起きのときにはまるで花が咲きほころぶかのように素直に快感をねだり、あえぎ、感じていることを敏感に知らせてくれる。
その姿が何よりそそられてしまってついタガが外れてしまうのだ、とは、彼は気がつかない。
いや、言ったところで彼は信じないのだ。
自分がどれほど魅了させる容姿を持ち、目をひきつけてやまないオーラを放っているかを。
僕は毛布を持ちあげて、悠季のあたたかな背中にぴったりと寄り添った。
僕の指にぷつんと触れてくる彼の乳首を撫で、くりくりと悪戯するとぴくりとからだを揺らした。
ここは彼が敏感に反応してくれる場所だ。ほら、もう感じ始めている。
起こしてしまうような愚をおかさないように、手を下へと移動することにした。
なめらかな腹を楽しみながらたどっていき、今はぐっすりと眠っている悠季の昂ぶりを手に収めた。
まだくったりとして、本当に昂ぶってはいないそれを、僕の手の中でゆっくりと目覚めさせていく。
「んん・・・・・」
眠っていても感じ始めているのだろう。子供のようにむずがってみせた。
本当に彼は感じやすい。
感じやすい場所は多くあり、僕は知り尽くしている・・・・・。
いや、まだだ。
まだ発見していないだけで他にも快感を得る場所があるかもしれない。それを知り尽くすにはまだまだ時がかかりそうだ。
日によって感じやすい場所は変化し、新たな場所が現れてくるのだから。
僕は悠季のあちこちに触れ、唇や舌や手のひらやその他いろいろなやり方で、もっとも感じる場所を探していく。
そして手管の限りを尽くして、彼が引き返せないところに達するまで刺激していくのはとても楽しかった。
まるで花がほころびていくように色白な肌が薄赤く染まり、色めかしい生き物になっていく。
そんな彼を見るのは、こんな方法で起こされる彼にはいささか申し訳ないが、何度見ても飽きないものがある。
もちろんそれは僕の我慢の限りを尽くして得られるものなのだが、この後の楽しみが待っていると思えば愉悦は増すというものだ。
熱を帯び、僕の手のひらの上で固く反りかえってきた彼の昂ぶりを放して、その奥をほぐしにかかった。
出来れば僕の舌でほぐしてあげたかったのだが、今この姿勢では思いどおりにする前に本格的に目覚めてしまう。次善の手段を使って先に進む事にしたほうがよさそうだ。
もしここで目覚めたら彼は真っ赤になって逃げ出してしまうか。それとも怒ってベッドから立ち去ってしまうか。どちらにしても不本意な結果になってしまうだろう。
悠季は寛大な性格だから、引き返せなくなったところで目を覚ましたなら僕のしたことをとがめるようなことはしない。
自分もしたくなってしまったからしかたないと許してくれる。僕はそんな彼のやさしさにいつもつけこんでいるのだ。
枕元に用意してあったジェルを取り出して、冷たさに悠季が反応してしまうのを避けるために手のひらであたためてから奥まで差しこんだ。
弾力のあるそこは昨夜の行為の余韻を残していて、僕の愛撫を受けて従順に柔らいでくれた。
ぐっと奥に差し入れると、とたんにきゅっと引きしめられた。
「あ・・・・・う・・・・・ん」
意識が浮上仕掛けているのだろう。眉をひそめてため息をもらした。
ぐるりと奥まで指を入れてジェルを塗り込めた。
「う・・・・・んんっ」
ぴくぴくと瞼がふるえる。
覚醒は近い。
もう少し待っていてください。
僕は片足を持ち上げると、痛いくらいに脈打っている僕の昂ぶりをぐっと押しこんだ。
たっぷりと塗ったジェルと充分なほぐしとで、そこはあっさりと僕を呑み込んでいった。
ひゅっと息を呑む音がする。
「な、何?」
ぱっと悠季の目が開いた。
驚愕の表情が浮かべられていたのは当然だったが、その瞳が濡れているのを見て満足した。
「お早うございます」
僕が挨拶すると、ぎゅっと昂ぶりが締め付けられた。
うっ・・・・・!
熱く包みこまれ引き絞られて、あっという間に暴発寸前まで高まってしまった。
「圭、君何をしてるんだよ」
眉をひそめて睨んできた。
どんな状況にあるのかを知るにつれて、不機嫌になってきたらしい。
まあ、当然のことではある。目覚めたとたんに、セックスを強要されていたとなれば。
だが僕に返事をする余裕はなかった。
うめき声をこらえるのがやっとのこと。平静な顔をしていることも難しかった。
こんなにも早く暴発するわけにはいかないではないか!
何とか息を整えて快感をやり過ごすと、睨んでいる彼に向き直って用意してあった言い訳を告げた。
「このまま抱いてもいいですかと聞いたのですが。君が承諾して下さったので喜んでこうしています」
「そ、そんなはず・・・・・!」
悠季は目を泳がせて、必死であいまいな記憶を探し回っているのだろう。本当に自分がそんなことを許したのかどうか。
素直な彼はいつもこうやって誠実に接してくれる。
そんなことは言っていないはずだ、と言い出す前に僕はゆるりと腰を動かした。
「あんっ!」
既に火のついていたからだは、新たな快感に身を震わせた。
「気に入らないのでしたらこのままやめますが」
ぐいっと抜ける寸前まで身を引いた。
「だ、だめっ!」
ここで止められたらたまらないといった風情で、悠季は急いで僕の腰に足を絡めて押し付けてきた。
「しかし君に無理強いをしたくはありません」
口先だけの言葉。
やさしい悠季がそんなことを言われたら嫌とは言えなくなることを僕はよく知っているのだから。
「・・・・・ばか」
甘くなじるような口ぶりと共に、上目づかいに僕を見る目はなんて色めかしいことだろう!
いけないですよ、悠季。
そんな色香をふりまいては、僕は止めることが出来なくなります!
僕はうめいて、そのまま悠季を襲いかかっていた。
そうして彼は二度目の失神をすることとなってしまい、僕は喜んで悠季の世話にはげむことになった。
気がついた彼に水を運び、後始末をしてから彼の好みの腕枕を貸して抱き寄せた。
すみません、悠季。
君が目覚めたら、君を思いやる大人の男に戻って、立派に振舞ってみせます。
ですから今だけわがままな男になってしまった僕を許して下さい。
赤ん坊返りをして君に甘えてしまった愚かな男を。
僕よりずっと大人な君に、僕は許しを乞う。
きっと君は目を覚ますと『しょうがない男だね』と苦笑をむけてくることだろう。
その優しさが僕は何よりも愛おしい。
愛しています、悠季。心から。
morning callとは名ばかりの話(笑)
悠季に起きて欲しかったのは、意識だけではなかったようです。(爆)
2011.5/12 UP