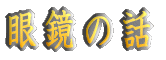
「ただいまぁー」
玄関から愛しい悠季の声が聞こえてきた。元気そうに聞こえるが、どこか上調子なのは疲れを隠そうとしているからだろうと思われた。無理も無い。今回のツアーは数県をまたぐ長期のものだった。
悠季は僕が立ち上げたオーケストラの他に大学の講師を務め、更に悠季自身のコンサートツアーという忙しいスケジュールをこなしている。だがこれが終われば少しは余裕が出来るはずだ。数日は二人でゆっくり過ごせるはずだから、疲れを癒せばいい。
「お帰りなさい。お疲れ様でした」
「うん。疲れたぁ」
いつものようにやさしい微笑みを浮かべてキスに応えてくれた。
「飛行機が遅くなったから予定より帰りが遅くなっちゃったんだ。いくつか持ち帰ってきた荷物もあるんだけど、邪魔になるからモトさんに持って行ってもらったから、明日にでも事務所に行って貰ってこなくちゃ・・・・・あっ!?」
楽しげにしゃべりながら音楽室へと向かっていると、ふいに立ち止まった。
かちゃ・・・・・。
軽くて小さな音がしたかと思うと、悠季の眼鏡が床にころげ落ちていった。
いったいどうしたのかと思いながら、僕の手元に転がったそれを拾いとって手渡そうとして、異変に気がついた。
「悠季、壊れているようですが」
「えっ、そうなの?」
ぎょっとした顔をした悠季に手渡したのだが、どうやら眼鏡のふちの部分がはずれてレンズがとれてしまっているようなのだ。部屋の隅に転がっていったレンズは見つけたが、なぜ壊れてしまったものか。
「あちゃー、眼鏡の枠をとめるビスがとれちゃってるよ。うーん、小さいから探しても見つからないだろうなぁ」
「そうなのですか?」
「うん、ほらこれ」
手渡して見せてくれたが、枠をとめるビスはとても小さい。外れていない方を見ると、おそらく1ミリほどしかないのではないだろうか。
「探してみましょう」
「ああ、いいよいいよ!今ここで外れたのかどうかもわからない。ビスが取れても外れなかったのかもしれないし。それにこんなに小さなビスだもの、見つけられるとは思えないよ」
「ですが、ないと不便でしょう?」
悠季の視力は矯正なしでは生活に支障をきたす。
「そうだけど、替えの眼鏡があるから・・・・・って。うぁー、しまった!荷物の中に入れちゃってたよ」
頭を抱えてうめいている。たまたま荷物をマネージャーに預けていたのが裏目に出たようだ。
「でしたらこれから元くんに電話して持ってきてもらいましょう」
「だめだよ!もう時間が遅いんだから悪いよ。ずっと長く同行してもらっていたんだ、宅島くんも待ちわびていただろうから奥さんを呼び戻すなんて気の
毒すぎる。明日の朝、眼鏡屋さんに行って修理してもらえばいいんだから、無茶を言っちゃ悪いよ」
良識的で遠慮深い悠季は相手に気を使う。
「それでは車を出します。代わりの眼鏡を買いに行きましょう。都心に行けば、この時間でもやっているところがあるはずです」
「いい、いい。そこまですることないって。明日までのことなんだ。家の中なら眼鏡がなくても大丈夫だよ」
そう言って僕に気を遣わせまいとしているが、表情は少しかたい。悠季は近眼に加えて乱視も入っているから、視界がぼやけていていて不安なはずなのに。
普段のてきぱきと物事を進めるきりりとした表情と違って、どこか焦点が合っていないまなざしは幼子のように不安げで、ひどく庇護欲をそそった。
思い出してみれば悠季が眼鏡をせずに長時間素顔を見せてくれていたのは、風呂やベッド以外ではイタリアでのカルナヴァーレのときの仮装をしたときと、八坂の事件でやはり眼鏡を壊してしまったときくらいだろう。
カルナヴァーレに出かけたときはすぐに仮面をかぶってしまったし、八坂の事件の頃は悠季はまだ僕に心を許していなかったから、こんなふうな心細そうな素の表情をしていなかった。
それだけ今は僕に心を許しているということだと思えば、いっそうのいとしさを感じてしまう。
「では、今夜は僕が君の『佐吉』となってかしずきましょうか」
「僕は『春琴』かい?それは嫌だよ。僕はわがままなお嬢様って柄じゃないし」
悠季はちょっと眉をひそめた。
ふむ、例えが悪かったようですね。
「失礼しました。では忠実な執事として今夜は君にかしずくことをお許しいただけませんか?」
「また召使ごっこかい?好きだねえ」
表情がゆるみ、 ごくごく小さなため息を一つつくと、うなずいた。
「君がそうしたいっていうなら、いいよ、君の好きなように」
どうやら悠季は僕のわがままを許してくれるようだ。先ほどのため息は、『しょうがない人だね』といったところだろうか。
「ええ、君の忠実な召使ならば、何度やっても楽しいものですから」
悠季の肌に触れるのは喜びなのだから。
「では、ご主人様。風呂にご案内しましょう。疲れているでしょうから、風呂上りにマッサージもされたほうがよいと思いますよ」
彼の背を押してうながしたのだが、なにやら疑わしげに僕を見る。
「・・・・・で、何をしたいわけ?」
『何』とはどういうことだろうか?はて・・・・・ああ、もしかして、風呂場で何か仕掛けてくるのではないかと疑っている?僕としては素直に希望を尋ねただけだったのだが。
「おや、風呂場でふらちなことをしてかすのではないかと考えられましたか?」
「・・・・・そんなことないよ!」
強い口調で否定してくれたが、その前のためらいは何を意味しているものか。
内心でそれを期待していた?いや、頬や耳はいつもの色、赤くなってはいない。それに目も潤んではいない。では、彼が望んでいることは何か・・・・・?
考えていて気がついた。
普段のときならばこんな言葉遊びを交えた誘惑や前戯めいたいたずらを喜んでくれるのだが、今夜の悠季は疲れて帰ってきたばかりだ。気を張って重圧のかかるステージをこなし、ようやく開放されたところ。気が利いたやりとりなどする余裕はないということなのだろう。まして、今は眼鏡もなく、視界も不安定なのだから。
ならば彼が望んでいるのは、何も気を使うことなく素直に甘えたいということなのだろう。
ええ、安心して身をゆだねてください。たっぷりと甘やかして差し上げましょう!
悠季の手を握りとり、もう片方の手は腰へと添えて風呂場へとエスコートする。やはり夜ということもあって不安だったらしく、黙って素直についてきてくれた。
風呂に一緒に入ると、隅々まで丁寧に洗ってあげた。
耳を赤くして恥ずかしがった彼は自分でやるからと言いはっていたが、『僕のお世話では気に入りませんか?』と言えば困った顔をして黙り込んだ。
丁寧に泡を洗い流すとそのまま一緒に湯船へと入った。
彼の背中を抱いてツアー中のあれこれと土産話をしてくれるのを聞いているうちに、目元に残っていた緊張も緩んできたようだった。
ほんのりと上気したところで風呂場から脱衣所へと誘導した。
「さあ、どうぞ」
「う、うん」
バスタオルを広げて包み込んであげるとおとなしく身を任せてくれた。抱いた感触が少しやせたように感じられて、明日のメニューを設定しなおした。彼の食が細いわけではないのだが、無理をするとすぐに体重に現れてしまう性質なのだ。
バスローブを着せかけ、二階への階段をエスコートし、寝室へと入った。
「さあ、マッサージをしましょう」
「あ、はーい。よろしく」
悠季をベッドにうつぶせにすると、ゆっくりと足の裏、ふくらはぎへとマッサージしていく。
「う・・・・・ん、気持ちいいよー」
どこか語尾がゆるんだ口調は悠季がリラックスしているというあかし。肩や手のひら背中とすすめていくと、うとうととし始めたようでやがて安心しきった
小さな寝息が聞こえてきた。
悠季が帰ってくるまでの僕は何日も待ちわびていたからと、今夜は抱きしめて情熱的な夜を過ごしたい。いや朝まで抱き合いたいとさえ熱望して指折り数え、浮かれて帰宅を待っていたものだ。
しかし、安心しきって身をゆだねてくれる悠季を眺めていると、僕のわがままや貪欲な情欲は泡のように消え去っていき、落ち着いた気分へと鎮まっていく。
このまま抱きしめたまま眠りにつくのも悪くない。彼は帰ってきてくれたのだから。
僕はそっと隣へと身を滑り込ませると、そっと息を吐いた。
「・・・・・ねえ、圭」
甘くかすれた声が隣からささやかれた。
抱いて。
と耳元につぶやくように吹き込まれ、一瞬にして僕の平穏な気分は霧散してしまった。
ふわりと香るのは先ほどのシャンプーの残り香。僕と同じもののはずなのに、なぜか僕の香りよりも甘く、媚薬となって僕を誘う。
信頼しきった柔らかな微笑が、窓からのわずかな明かりの中でもよく見えた。
「今夜は、甘やかしてさしあげるのでしたね」
「・・・・・うん」
少し恥ずかしそうな顔をしながら手を伸ばし僕の首を引き寄せてきた。甘いキスを互いに堪能し、手のひらと指と唇とあらゆるもので悠季のイイところを愛撫する。
首筋や乳首のようないつも必ず敏感に感じてくれる場所だけでなく、その時々によって敏感に反応してくれる場所を探し出す。
彼は日によって過敏なほどに反応してくれるところが変わるのだ。あるときは鎖骨を舐め軽く歯をたてると鋭敏に反応し、あるときはわき腹から肋骨に沿って舐めてあげるとそれだけでイキそうになるほど感じてくれる。
宝探しのようにその場所を毎回見つけだすことは、新鮮であり、喜びでもある。
ただ気をつけなければいけないのは、あまり執拗に愛撫することで悠季の機嫌を損なうことがないように気をつけなければいけないことだ。
以前、彼のあえぎや感じ入った声がもっと聞きたくて執拗に責めたためにひどくスネられてしまったことがある。平身低頭して謝罪し、なんとか許してもらえたのだが、あのような失敗の轍は二度と踏みたくない。
官能に濡れた声で悠季が啼く。すすり泣き、僕の首にしがみついてかすれた声で、もっと とねだる。
ああ、これこそが僕の最愛の恋人。
僕たち二人は、何日も会えなかった寂しさを互いの熱で埋めて、満ち足りた気分でぐっすりと眠り込んだ。
翌朝もまた悠季を台所へとエスコートすると、準備してあった朝食を並べた。視界がぼやけていても食べやすいようにチーズ入りのオムレツにボイルしたソーセージ。温野菜のサラダとトーストにコーヒー。
「また腕を上げたみたいだね。とっても美味しいよ」
にこりと悠季が笑う。
「光栄です」
二人で食べる食事には何よりも強力で美味な調味料が入る。愛情と言う名の調味料が。
昨日までの僕の食事のなんと味気なかったことか。
「食べ終わったら眼鏡屋へ行きましょう。車を出します」
「えー?電車で行けるよ。大学に行く途中でちょっと修理を頼めばいいと思っていたんだし」
「僕を不安で苛むつもりですか?きみがどこかで事故でもおこさないかと心配で落ち着きません」
「そんなこと」
「ないとは言えないと思いますが。それに一つは家に予備を置いて置いたほうがいいと思いますよ。作りましょう」
「・・・・・うん、そうだね」
素直に承諾し、僕たちは車で出かけ都心までのわずかなドライブを楽しんだ。
早朝でも開店している眼鏡店は、出かける前に調べておいた。
悠季は修理と一緒に予備の眼鏡を注文し、そのまま大学まで送っていった。
さて、僕の方の仕事はといえば、簡単なインタビューだけで、終わればそのまま帰宅できる。帰りに出来上がった眼鏡を受け取っていく事になっている。ついでに、悠季の好みそうな品を買っていくことにしようか。
今夜はゆっくりと二人で夕食を楽しもう。穏やかな夜を過ごすのだ。
悠季が家に戻ってきてくれた。帰ってきてくれるまでのどこかモノクロな色彩をした日々は終わり、輝度の上がったかのようだ。
そう、いつもどおりの穏やかで楽しい日々がまた始まるのだ。
| 素材サイト様でこの『眼鏡』のイラストが配布されているのを見たとき、 「これって悠季のために作られた素材に違いない!」 と思いました。(笑) なるべく日常の甘い話を心がけたのですが、甘さはどうでしょう? 念のために、途中出てくる佐吉と春琴とは『春琴抄』のこと。 |
2015.4/21 up
